日本通信、「原価のイコールフッティング」問題を総務省に訴え
2012年12月3日
日本通信、「原価のイコールフッティング」問題を総務省に訴え
日本通信株式会社(以下、「当社」という)は、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、「ドコモ」という)が通信原価に関して、自社の一部顧客向けには低い原価を、一方で自らの競争事業者である接続事業者には高い原価を用いることで、法が定める公平な競争環境を著しく阻害している問題について、電気通信事業法第172条の規定により、総務省に意見申出を提出いたしました。
電気通信事業法第33条及び第34条で定める一種指定電気通信設備(NTT東西)及び二種指定電気通信設備(ドコモ他)を持つ電気通信事業者は、設備事業者の側面とサービス事業者としての側面の両方を有しています。設備事業者としての側面からは、当該設備を「原価+適正利潤」を上回らない接続料で接続事業者に提供することで、接続事業者は、指定電気通信設備を持つ電気通信事業者のサービスと公正な競争を行い、その結果として、顧客サービスの低廉化と多様化が進展します(図1参照)。
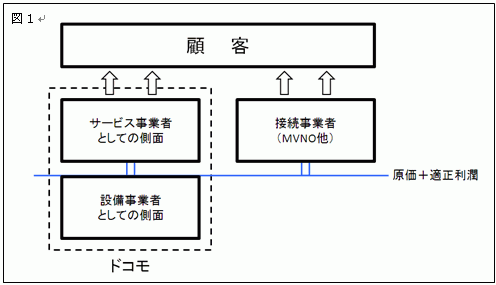
しかしながら、ドコモが一部の顧客向けに用いている原価と、接続事業者向けの接続料算定に用いている原価とは異なるものになっており、接続事業者に対しては、遥かに高額な原価、具体的には今日の段階では凡そ3倍の原価に基づく接続料になってしまっています。
当社はこの問題について、ドコモに是正を申し入れましたが応じられず、また総務省に対しても対処を求めてきましたが、進展が見られないため、本日、正式な形として意見申出を提出したものです。
様々な形態の通信事業者、即ちMNOやMVNOが、公正な競争環境のもとでお互いに切磋琢磨して競争することは、通信料金の低廉化や通信サービスの多様化を生み出し、利用者の利益に繋がります。従って、MNOやMVNOが、公正な競争環境に立脚する、つまりイコールフッティングは、通信事業の健全な発展の根幹にかかわる問題です。
当社は、2007年にドコモとの接続に関して総務大臣裁定を申し入れ、大臣裁定で認められた結果、2008年からドコモの通信網を用いたMVNO事業を開始しました。その後、MVNO事業参入が相次ぎ、従来になかった月額定額980円のような低廉なサービスや、データ量単位(1GBまで使える等)、あるいは通信速度を制限したサービスなどの多様化も進んでいます。
しかし、原価に関するイコールフッティングが整っていない現状がこれ以上継続してしまうと、公平な競争環境が阻害され、利用者利益は確実に損なわれてしまいます。
当社は、既に日々の生活に密着し、かつ重要性を益々高めているモバイル通信が、様々なモバイル事業者の公平な競争によって更に発展していくよう、当社の役割を全うしていく所存です。
【背景】
当社は、2010年4月19日に、ドコモの法人顧客向け料金が原価を下回っている可能性が高いとして、総務省に意見申出を行いました(詳細は、2010年4月19日公表資料をご覧下さい)。しかしながら、同年6月18日付けで、総務省から明確な判断を回避する形の回答を得たことから、同年6月21日に、行政文書開示請求を行い(詳細は、2010年6月21日公表資料をご覧ください)、総務省の内部資料(ドコモが総務省に提出した資料を含む)を入手しました。この資料によると、ドコモは、法人顧客向けに将来原価を適用し、従って、当時の状況からは考えられない程の低価格の料金を提供していることが判明しています。
この事実と、接続料算定に用いる原価に関する事実の二つは、明確に原価の使い分けを示していることから、当社は、この問題を指摘してまいりました。
MVNO制度は、既に利用者利益を生み出し始めてはいますが、一方で、未だ未成熟な制度であり、このような新たな問題が生じていますが、公平な競争環境を構築・維持する観点から、早急な対処が求められています。
■日本通信について
1996年5月24日、日本通信は新たなモバイルサービス事業のあり方を提示するため生まれました。それから13年の歳月を経て、2009年3月、NTTドコモとの相互接続により「MSO事業モデル」を完成させ、それから2年弱でこのモデルの収益性を実証しました。ネットワークを効率的に運用する当社独自の先端技術やリアルタイムの認証技術などによって、ユニークな通信サービスをつくりだし、自社b-mobileブランド製品をお客様に提供するMVNO事業、及びメーカーやインテグレータ他のパートナー企業に提供するMVNE事業を展開しています。
MSO=Mobile Service Operator
※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



